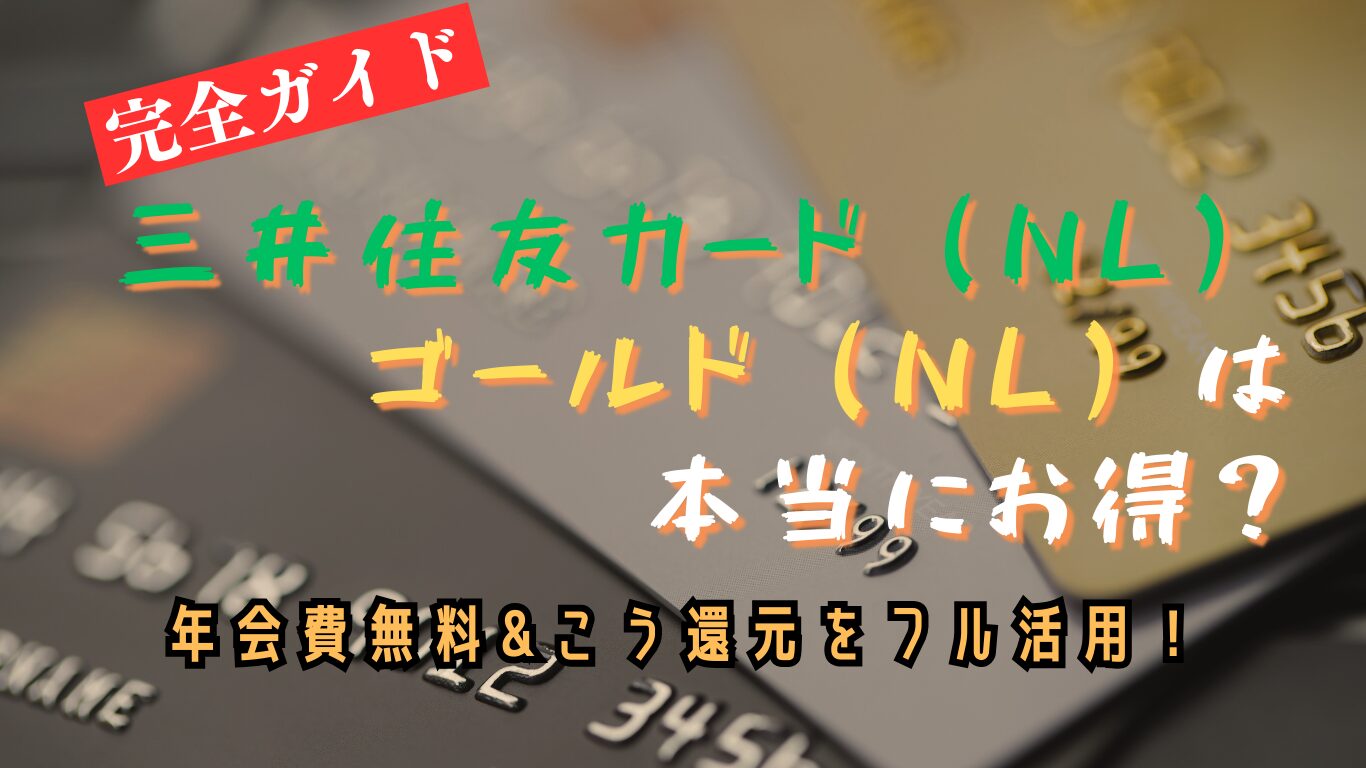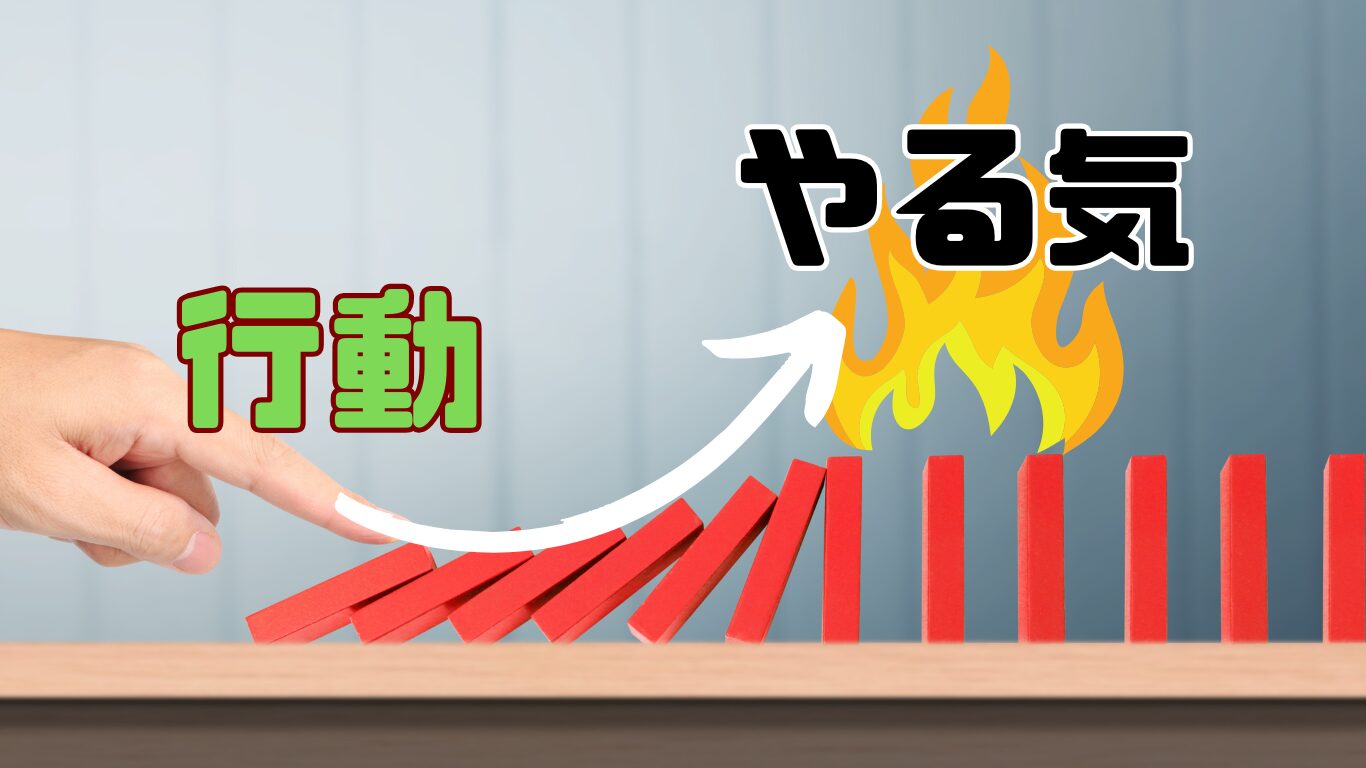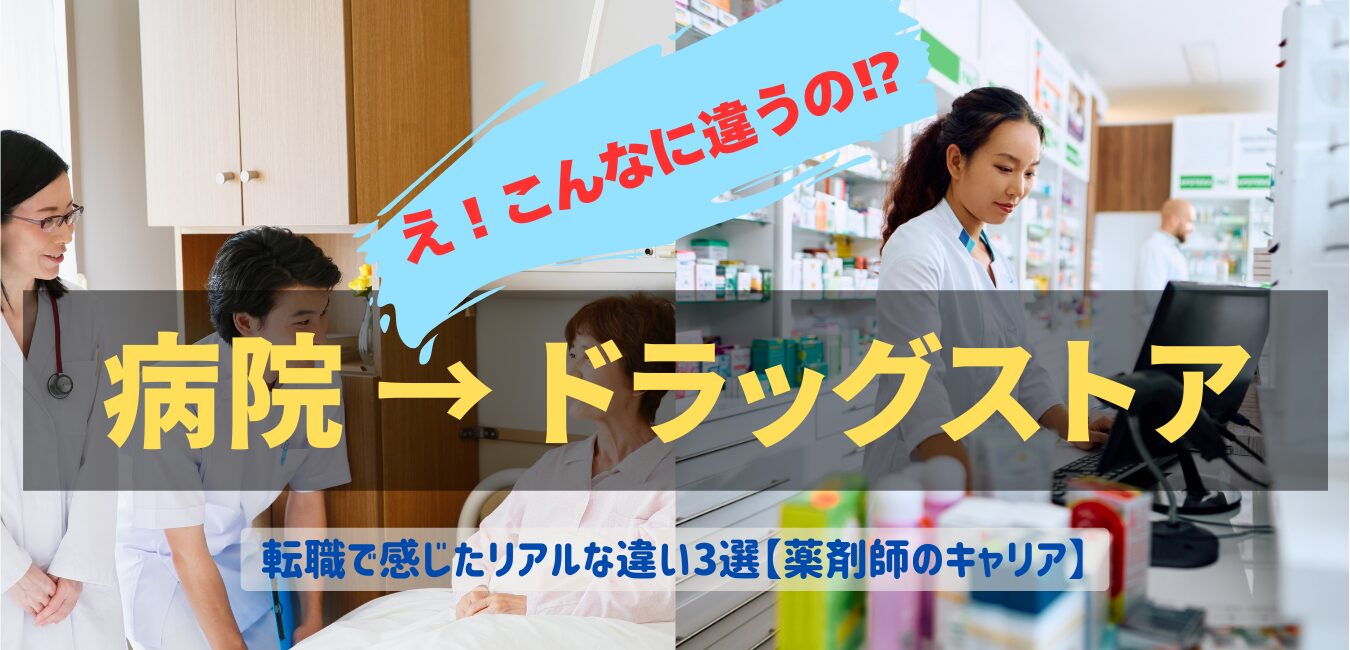初心者向け新NISA入門:新NISAとは?メリットや始め方をやさしく解説

2024年からスタートした新NISA(少額投資非課税制度)は、これまでのNISA制度を大幅にパワーアップした、初心者にも魅力的な投資制度です 。
20代~30代で投資未経験の方でも、新NISAの基本を押さえれば税金を気にせず資産形成を始めることができます。
この記事では**「新NISAとは?」という制度概要から、メリット、始め方、さらに人気の証券会社楽天証券 vs SBI証券**の比較まで、しっかり解説します。
「とりあえずこの記事を読めば、新NISAの基本がわかる!」という内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
新NISAとは?制度の概要をやさしく説明
新NISAとは, 2024年1月から始まった新しいNISA制度のことです 。
NISAは「少額投資非課税制度」という名前の通り、株式や投資信託の運用益(売却益・配当金など)が非課税になるおトクな制度です 。
通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、新NISA口座での投資ならその税金が0%(非課税)になります 。つまり利益まるごと手元に残るので、資産形成が有利になるのです。
新NISA最大の特徴は、非課税で投資できる枠が大幅に拡大&使いやすく改良された点です。具体的には次のようなポイントがあります。
旧NISAでは年間の非課税投資枠は最大120万円(一般NISA)または40万円(つみたてNISA)でしたが、新NISAではそれが合計360万円に拡大しました。
年間360万円までの投資なら運用益が非課税となります。
旧NISAでは非課税で運用できる期間に制限(一般NISAで最長5年、つみたてNISAで最長20年)がありましたが、新NISAでは非課税保有期間が無期限になりました。
ずっと非課税で保有できるので、長期投資に非常に有利です。
新NISAは終了年の決まっていた旧制度と異なり、恒久的な制度として今後も継続します 。
将来「制度が終わるから急いで売却」といった心配がなくなりました。
新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2種類の非課税枠が用意され、1つのNISA口座内で両方を同時に利用可能です。
旧制度では年間で一般NISAかつみたてNISAどちらか一方しか使えませんでしたが、新制度では例えば「毎月コツコツ積立+個別株へのスポット投資」を並行して行えます。
新NISAには一生涯で非課税投資できる総額の上限が設けられ、その非課税保有限度額は1,800万円と定められました。
このうち成長投資枠で使えるのは最大1,200万円までですが 、非常に大きな金額を非課税で運用できます。
また売却した分は枠が復活する仕組みで、売った翌年以降にその枠でまた新たに投資できる柔軟性もあります。
以上のように、新NISAは「長期でコツコツも、一括投資も、たっぷり枠で非課税運用できる」制度へと進化しています。初心者にとっても、最初の一歩を踏み出しやすい土壌が整ったと言えるでしょう。
新NISAの2つの投資枠(つみたて投資枠・成長投資枠)
新NISAでは非課税枠が「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つに分かれています。それぞれの概要を簡単にまとめると次のようになります。
| 投資枠 | 年間投資上限額 | 非課税保有期間 | 投資対象商品 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 (積立枠) | 年間120万円 | 無期限 | 長期積立に適した投資信託のみ | 毎月一定額をコツコツ積み立てる運用向き |
| 成長投資枠 | 年間240万円 | 無期限 | 株式・投資信託・ETF等(※一部除外あり) | 個別株やETFなど幅広い商品にまとめて投資可能 |
*※新NISA全体の生涯非課税投資枠は合計1,800万円(成長投資枠はその内最大1,200万円)です 。つみたて投資枠と成長投資枠の併用で年間最大360万円まで非課税投資できます。枠は**買付額(投資した金額)*で管理され、値上がりしても心配ありません (売却時にその分の枠が減り、減った分は翌年以降に再利用可能 )。
新NISAのつみたて投資枠は、旧つみたてNISAと基本的に同じく「指定された低リスクの投資信託」に長期積立する枠です。コツコツ積立投資向けで、対象商品も金融庁が定めた長期分散投資に適した投資信託のみとなります 。
一方、成長投資枠は旧一般NISAに相当し「株式やETF・投資信託など幅広い商品」に投資できる枠です 。こちらは一括投資や個別株投資も可能ですが、一部例外としてリスクの高い商品(レバレッジ型・毎月分配型の投信など)は対象外となっています 。どちらの枠も非課税で保有できる期間は無制限なので、売らずに持ち続ける限りずっと税金ゼロで運用できます。
初心者の方でも「毎月の積立で投資デビューしたい」「応援したい日本株を買ってみたい」といったニーズに合わせて、つみたて投資枠と成長投資枠を自由に組み合わせて使えるのが新NISAの魅力です 。まずは新NISAの口座を開設すれば、この2つの枠を使って合計年間360万円まで非課税投資が可能になります。
新NISAのメリット:初心者にうれしいポイント
新NISAには、投資初心者にとってもうれしいメリットがたくさんあります。ここでは主なメリットをいくつか確認してみましょう。
- 投資の利益が非課税:なんといっても最大のメリットはこれです。通常、株や投資信託の売却益・配当金には約20.315%もの税金(所得税・住民税)がかかります 。しかしNISA口座での投資なら税金0円 !利益を丸ごと受け取れるため、複利効果も高まり長期的な資産形成が有利になります。
- 長期運用に有利(無期限&大きな非課税枠):新NISAでは運用期間の制限がなく無期限なので、長期保有でじっくり値上がりを待つ投資に最適です 。また生涯1,800万円までという非課税投資枠は、将来に向けてコツコツ積み立てるのに十分な額と言えます 。若いうちから始めれば、長い年月をフルに使って大きな非課税運用益を狙えます。
- 柔軟に積立&一括投資できる:つみたて投資枠と成長投資枠を組み合わせて使えるため、自分の投資スタイルに合わせた運用ができます 。例えば毎月の積立投資で投資に慣れつつ、ボーナス時に成長投資枠で株式をまとめ買いする、といった使い方もOKです。売却したら枠が復活する仕組みもあるため、「一度枠を使ったらもう投資できない」という心配も少なく、柔軟に資産運用を続けられます 。
- 初心者でも始めやすい:NISA口座は誰でも18歳以上であれば開設可能です (※日本在住の方に限ります)。口座開設・維持費も無料で、ネット証券ならオンラインで手続きが完結します。NISA専用の商品ラインナップは初心者向けの投資信託も充実していますし、非課税というメリットが大きい分、少額から投資を始める動機付けにもなるでしょう。「とりあえずやってみる」にはピッタリの制度です。
こうしたメリットから、新NISAはこれから投資を始める20代・30代の強い味方になってくれます。もちろん元本割れリスクなど投資の基本的な注意点はありますが、税制面の優遇がある分リターンも期待しやすく、資産形成の第一歩として最適と言えるでしょう。
新NISAの始め方:口座開設から投資までの3ステップ
「新NISAをやってみよう!」と思ったら、具体的に何から始めれば良いのでしょうか?ここでは新NISAを始めるまでの一般的な手順を3つのステップに分けて紹介します 。難しい手続きはありませんので、ご安心ください。
図:新NISA口座開設は、Step1 金融機関の選択と口座開設申込、Step2 本人確認書類など必要書類の提出、Step3 口座開設完了後に非課税枠で投資開始、という流れで進みます。 新NISA対応の証券会社なら、ネットで手続きが完結し郵送書類のやり取りも不要です。

まず、新NISA口座を開設する金融機関を選びましょう 。新NISAは多くの証券会社や銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫などで取り扱いがあります 。初心者の方には、**ネット証券(オンラインの証券会社)**での口座開設が特におすすめです。ネット証券なら手数料が安く、取り扱い商品の種類も豊富で、スマホで手軽に取引できるメリットがあります。
有名なネット証券としては楽天証券やSBI証券のほか、マネックス証券、auカブコム証券などがあります。どの金融機関でも新NISAの基本的な非課税枠は同じですが、サービス内容や使い勝手が異なるので、自分に合いそうなところを選びましょう 。ポイント還元やツールの充実度など、後述する比較ポイントも参考にしてください。
※すでに2023年以前に旧NISA口座を持っていた方は、原則として同じ金融機関に新NISA口座が自動移行されています (旧NISAからの資産もそのまま非課税運用継続)。別の金融機関で新NISAを始めたい場合は、現在の口座で金融機関変更手続きが必要です。

金融機関を決めたら、実際にNISA口座開設の申し込みを行います 。ネット証券の場合、ウェブサイト上で「NISA口座開設」のボタンや案内を探し、オンラインで申し込み手続きを進めます。氏名やマイナンバー(個人番号)など必要事項を入力し、本人確認書類を提出すればOKです 。オンライン手続きなら、スマホ一つで完結し郵送の手間も省けます 。
口座開設の申し込み後、金融機関や税務署での審査を経てNISA口座開設完了の通知が届きます。新規にNISA口座を開く場合、申し込みから完了まで通常2~3週間程度かかることが多いです(時期によりますが)ので、余裕を持って手続きをしましょう。開設完了までは待つだけです。その間に「どの投資信託を積み立てようかな?」など、投資プランを考えておくとスムーズです。

NISA口座が開設できたら、いよいよ新NISAでの投資開始です。証券会社のサイトやアプリにログインし、**NISA口座(非課税口座)**を選択して商品を買い付けることで、新NISA枠を使った投資ができます。
初心者の方は、まずはつみたて投資枠で投資信託の積立から始めてみるのがおすすめです。例えば「月1万円をインデックスファンドに積立」など少額ではじめ、慣れてきたら成長投資枠で個別株やETFにチャレンジしても良いでしょう。買い付けた商品は自動的に新NISA枠に計上され、非課税で運用されます。
また、証券会社によってはクレジットカードで積立代金を支払う設定が可能で、カードのポイントがもらえるサービスもあります(後述の楽天カード・三井住友カードの例など) 。積立設定や購入方法は各社の案内に従って進めてください。
こうして新NISAで購入・積立した金融商品は、売却しない限りずっと非課税で運用されます。定期的に評価額や積立状況を確認しつつ、無理のない範囲で続けていきましょう。途中で売却しても利益は非課税ですし、売却した分の非課税枠は翌年以降に再利用できます 。まさに初心者にとって使い勝手の良い制度です。
証券会社の選び方:楽天証券 vs SBI証券を比較!
新NISAを始めるにあたり、「どの証券会社で口座を開くか」は多くの人が悩むポイントです。特に人気の高い楽天証券とSBI証券はどちらも魅力的で、それぞれに強みがあります。ここでは楽天証券とSBI証券の新NISAに関するサービス内容を比較し、選び方の参考にしてみましょう。
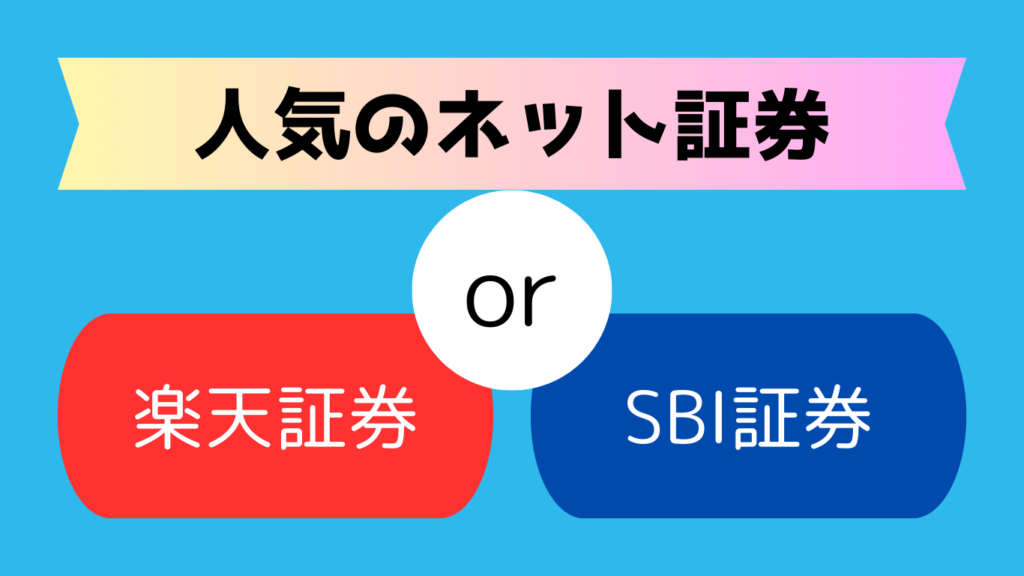
楽天証券とSBI証券の基本スペックは?
結論から言えば、楽天証券とSBI証券は新NISAの取り扱いにおいて基本的なスペックはほとんど同じです 。どちらも日本を代表する大手ネット証券であり、新NISAの非課税投資枠(年間360万円、生涯1,800万円)は当然共通です。国内株式や投資信託の取扱商品数も遜色なく充実しています し、新NISA口座の売買手数料は無料なのも同じです 。スマホアプリやサポート体制も整っており、初心者が新NISAを始める口座として両社とも申し分ないでしょう。
以下に主要な項目で両社を比較した表を示します。
| 比較ポイント | 楽天証券 NISA | SBI証券 NISA |
|---|---|---|
| 取扱商品 | 国内株式(東証上場全銘柄)・米国株・ETF・投資信託 など | 国内株式(東証全銘柄+札証・福証など地方市場銘柄も)・米国株・新興国株式・ETF・投資信託 など |
| 投信積立の頻度 | 毎日積立・毎月積立に対応 | 毎日積立・毎週積立・毎月積立に対応 |
| 最低積立金額 | 100円から可能 | 100円から可能 |
| 投資信託本数 | 2,000本以上(主要ネット証券でトップクラス)※ | 2,000本以上(同等)※ |
| NISA口座の売買手数料 | 無料(株式売買手数料ゼロ) | 無料(同左) |
| クレカ積立ポイント還元 | **楽天カード決済で1%**の楽天ポイント還元 (上限月5万円まで) | **三井住友カード決済で0.5%~最大2%**のVポイント還元 (カード種別・利用額に応じ変動) |
| 投信保有ポイント (※投資信託の残高に応じて貯まるポイント) | 対象ファンドはわずか6銘柄(楽天グループの自社ファンドのみ) | ほぼすべての投資信託がポイント付与対象 (月平均残高に応じてVポイント付与) |
| 連携サービス | 楽天ポイントが貯まる・使える(他の楽天経済圏サービスと連携) | Tポイントが貯まる・使える(※別途SBIグループの提携サービス利用)/住信SBI銀行と連携可能(預金金利優遇など) |
| スマホアプリ | 「楽天証券アプリ」「iSPEED」など初心者にも見やすいアプリが充実 | 「SBI証券アプリ」「HYPER株アプリ」など高機能ツールが豊富(2023年に初心者向け新アプリもリリース) |
※投資信託の取扱本数はいずれも2023年時点で2,000本超と業界最多水準です。
表のとおり、基本的な使い勝手や商品ラインナップに大きな差はありません。ただしポイント還元サービスにいくつか違いが見られます。特にクレジットカードでの積立と投信保有ポイントの2点は、両社の特徴が分かれる部分です。
- クレカ積立のポイント還元:楽天証券は楽天カードでの投信積立に対し一律1%の楽天ポイント還元を実施しています 。毎月最大5万円まで積立可能で、上限の5万円積み立てれば毎月500ポイント獲得とかなりおトクです。一方SBI証券も三井住友カード(NLなど)での積立にポイント還元がありますが、**還元率は0.5%~2.0%**と利用状況によって変動します 。一般的な条件下では0.5%~1.0%程度となるため、ライトユーザーなら楽天カードの方がポイントを貰いやすいでしょう 。逆に三井住友カード(プラチナ等)を活用して年間利用額が多い人はSBIで高還元を狙うことも可能です 。
- 投信の保有ポイント:SBI証券ではすべての投資信託が保有ポイント付与の対象となっています 。投資信託を持っているだけで毎月少しずつVポイントが貯まる仕組みで、塵も積もれば馬鹿になりません。楽天証券は2022年以降このサービスを縮小し、現在ポイント付与対象は楽天グループの特定投信6銘柄のみとなっています 。一般的な投信を買う場合、ポイントが付くのはSBI証券の方と考えてよいでしょう 。
楽天証券とSBI証券、どっちがおすすめ?
では結局、新NISAを始めるなら楽天証券とSBI証券のどちらが良いのでしょうか?結論として、どちらも優秀なので自分の重視する点で選ぶのがおすすめです。
積立の1%ポイントでお得に積立したい方や、シンプルで分かりやすいサービスを重視する初心者の方に向いています。
口座開設数も楽天証券は約600万口座と非常に多く 、初心者にも人気です。
幅広い商品への投資チャンスを求める方(例:外国株やIPO、新興市場の銘柄も積極的に買いたい方)や、ポイントを最大限に活用したい上級者志向の方に向いています。TポイントやPontaポイントなど他社との連携もあり、サービス総合力で選ぶならSBI証券でしょう。
口座数も業界トップクラス(約536万口座)で信頼感があります 。
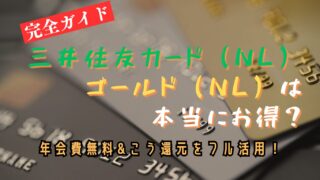
迷った場合は、身近で使いやすく感じる方を選んでまず始めてみることが大切です。 両社とも口座開設・維持費は無料なので、「合わないな」と思ったら翌年以降に金融機関変更することも可能です(※同一年内に2社でNISA口座を開設することはできません)。まずはピンときた証券会社で新NISAの第一歩を踏み出しましょう。
ちなみに僕は楽天経済圏(楽天市場、楽天銀行、楽天モバイルなど)を多く利用しているので、楽天証券でNISA口座を開設しています。
まとめ:新NISAで資産形成の第一歩を踏み出そう
新NISAは、これから投資を始める初心者にとって非常に魅力的で始めやすい制度です。**「新NISAとは?」**という基本からメリット、始め方、証券会社の選び方まで解説してきました。
- 新NISAは2024年スタートの恒久化された非課税投資制度。年間最大360万円、生涯1,800万円までの投資から得られる利益が非課税 。
- 運用益非課税&無期限保有なので、長期の資産運用に最適。
税金20%がゼロになるメリットは大きい 。 - つみたて投資枠(積立用の枠)と成長投資枠(幅広い商品用の枠)の2つを使って、自分のスタイルで運用可能 。
- 口座開設はネットで簡単、手数料無料で誰でも始めやすい。
- 楽天証券・SBI証券といった大手ネット証券なら充実したサービスで安心。
ポイント還元など独自のメリットにも注目して、自分に合うところを選ぼう。
まずは少額からでも非課税投資のメリットを体感してみることが大切です。新NISAで得た利益はすべてあなたの資産形成に直結します。若いうちから時間を味方につけて運用を続ければ、将来大きな財産を築ける可能性もあります。
難しく考えすぎず、「やってみる」ことが成功の第一歩です。ぜひ新NISAを活用して、賢くお金を増やす経験を積んでみてください。あなたの新NISAデビューを応援しています!